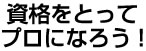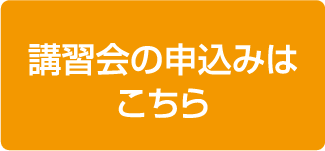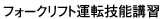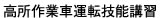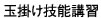| 昨年の熱中症による死亡は全国で47名にのぼり、過去10年間で最も多く、それまで最多であった平成13年(24件)のほぼ倍となりました。業種別では、建設業17名、製造業名農業6名運送業2名、警備業2名、林業1名、その他業種10名です。製造業、運送業、その他業種の発生状況概要を下記に掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製造業せ発生したもの
製造業の全ての事例で、自覚症状の有無にかかわらず、水分、塩分の補給を行わせる措置がありませんでした。また、8人の事例でWBGT測定に基づく予防対策がありませんでした。 運送業で発生したもの
その他業種で発生したもの
平成22年の発生の特徴は次のとおりです。 ・全体の53%(25名)が7月に発生しており、気候の変化に体の熱順化が追いつかなかった可能性があります。また、全体の約43%(20名)が午後3時~4時台の発生です。 ・全体の63%(30名)が作業開始から3日目までの発生です。また、61%(29名)が作業開始10日以上での発生です。 発生防止の措置のポイントとして次の事項を考慮してください。 ・WBGT値を計測し、これを指標として作業の管理を行うことが望ましい措置です。 ・水分・塩分の摂取確認表などにより、自覚症状の有無にかかわらず定期的に水分・塩分の補給を行う事を管理することが必要です。 ・事務室内については、省電力に取り組む場合でも出来る限り室温28℃を維持し、扇風機の使用など冷房効果の向上に取り組むことが必要です。 |
admin のすべての投稿
労働保険事務組合からのお知らせ
労働保険事務組合からのお知らせ
平成22年11月、西宮労働基準協会は、労働保険事務組合成立の許可を受け、現在多くの会員企業様にご加入を頂いているところです。
当事業組合は、多くの企業様にお気軽にご利用いただけるよう、諸費用も大変リーズナブルに設定させていただいております。
またご加入を頂いておられない会員企業様は、是非この機会に加入をご検討ください。
□ 労働保険事務組合加入のメリットは・・・
メリット1 事業主の労災特別加入ができる!社長さんも労災に加入できます!!
(最近の建設事業では、事業主の労災特別加入が入札の条件とされる傾向にあります。)
メリット2 経費節減につながる! 他の事務組合の費用と比較してください!!
|
労働保険事務組合 西宮労働基準協会 |
A労働保険事務組合の場合 | 労働保険事務組合Bの場合 | |
| 入会金 | 0円(※1) | 10,000円 | 0円 |
| 月会費 | 1,000円(※2) | 2,000円 | 5,000円 |
※1…西宮労働基準協会の会員に限る
※2…従業員数15人以下の場合。(16人以上の場合のゲッ会費はお問い合わせください)
加入の申し出、詳細のお尋ねにつきましては、下記までお電話ください
西宮労働基準協会 労働保険事務組合担当 TEL:0798-33-4939
衛生推進者養成講習会のご案内
衛生推進者養成講習会のご案内
常時10人以上50人未満の労働者を使用する下記の業種以外の事業場(例えば、病院・銀行・保険代理店など)には、
衛生管理業務を担当する推進者の選任が義務づけられています。
この度、標記の講習会を実施することになりましたので、選任が義務付けられました事業場はぜひ受講されますようご案内いたします。
(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業・燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業)
1 日時 平成25年8月6日(火)12:40~18:25
2 場所 西宮市立勤労会館4階第8会議室
・西宮市松原町2-37 ・tel: 0798-34-1662
3内容
| 時間 | 内容 | 休憩時間 |
| 12:40~12:50 | 受付 | |
| 12:50~13:00 | 開講あいさつ、説明 | |
| 13:00~15:05 | 作業環境管理及び作業管理 | 14:00~14:05 |
| 15:05~15:10 | ||
| 15:10~16:10 | 健康の保持増進対決 | 16:10~16:15 |
| 16:15~17:15 | 労働衛生教育 | 17:15~17:20 |
| 17:20~18:20 | 労働衛生関係法令 | |
| 18:20~18:25 | 修了証の交付 |
4受講料
・受講料4,200円(税込) ・テキスト代945円(税込)
5 定員
70名(定員になり次第締め切ります)
労災保険実務担当者講座
労災保険実務担当者講座のご案内
労災保険の実務担当者に対し、実務上良く起こり得る問題で特に重要なもの、
また、誤りを犯しがちなもの等を具体的に取り上げて研修いたします。
ご参加いただきますようご案内いたします。
記
1 日時 平成24年3月6日(火)14:00~17:00
2 場所 西宮市立勤労会館4階第8会議室
西宮市松原町2-37
0798-34-1662
3 内容 〇労災保険〔補償〕給付の時効
〇こんな場合業務上になります
外出中、勤務時間中、出張中、休憩時間中
〇保険給付について
4 講師 茶園 幸子 氏 (社会保険労務士)(元神戸東監督署長)
5 受講料 4,000円(資料代込)
6 申込み締切日 2月29日
みなし労働時間制
| Q 当社では外勤営業員の労働時間を把握するにあたり、みなし労働時間制を採用することを検討していますが、一方で、事業場内で報告書を作成したり、上司とミーティングを行う等の内勤があり、外勤と内勤を合わせると所定労働時間内で収めるのが困難な事態にあります。この場合、どのように取り扱えばよいでしょうか。 |
| A 事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定は、労働基準法第38条の2にあります。その第1項において、「労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされることとなっています。このみなし労働時間制は、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務を対象としています。使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合、すなわち、「事業場において訪問先、帰社時刻など当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合」などはみなし労働時間制の適用はありません。実際、訪問先、用件等の業務計画をあらかじめ作成し、上司の決裁を受けた上で外勤を行うケースは多く、そのような場合にみなし労働時間制を採用している場合は誤った取り扱いであるとえます。さて、ご質問のように、1日の労働時間のうち、一部を事業場外で業務に従事する場合についても、その日の労働時間を算定することが困難な場合には、このみなし労働時間制の対象となります。しかし、ご質問のように、外勤と内勤を合わせると所定労働時間内で収めるのが困難な実態にある場合に、実態を無視して安易に「所定労働時間労働したものとみなす」わけにはいきません。労働基準法第38条の2第1項の但し書きにおいて、「当該業務を遂行するためには通常指定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務にかんしては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」こととなっています。「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」とは、外勤の遂行に通常必要とされる時間と内勤の時間とを加えた時間が、所定労働時間よりも長い場合が該当します。例えば、ご質問のケースにおいて、所定労働時間が8時間で、外勤の遂行に必要とされる時間が6時間である場合に、内勤の時間が2時間を超えて労働した日に外勤に従事した場合にはこれに該当することとなります。「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であり、各日の状況や従事する労働者等によって実際に必要とされる時間には差異があると考えられますが、平均的にみれば当該業務、すなわち外勤の遂行にどの程度の時間が必要かということになりますので、外勤の遂行に通常の状態で客観的に必要とされる時間が6時間であれば、事業場内で労働した時間が3時間である日には9時間、4時間である日には10時間労働したものとみなされます。すなわち、労働時間の一部を内勤した日の労働時間=みなし労働時間制によって算定される外勤の時間+別途はあ行くした内勤の時間となります。なお、労働基準法第38条の2第2項において、当該業務の遂行に通常必要とされる時間について、労使協定を締結していればその協定で定める時間とすることとなっています。外勤と内勤を合わせると所定労働時間内で収めるのが困難な実態にある場合、外勤の遂行にどの程度の時間が必要であるかについては、業務の事態を最もよく分かっている労使間で、その実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当だからです。ですから、外勤が取り扱い商品、担当地区等によって類型化され、それぞれごとにその業務の遂行に要する時間に差異があるのであれば、労使協定ではそれぞれごとに時間数を定めることになります。また、どの程度に区分するかについても、労使間でよく協議することが必要になります。よって、実態に即した労働時間の算定を行うために、出来る限り労使協定を締結することが望ましいといえます。なお、労使協定は、協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には様式第12号により所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。上記の例のように外勤の時間が法定労働時間を超えないのであれば、届け出る必要はありませんが、外勤と内勤を合わせ法定労働時間を超えることになつときに届け出る時間外労働に関する協定に、この労使協定のの内容を付記して届け出ることもできます。(注:任意です)この場合は様式第9号の2を使用して届け出てください。 |
年俸制の従業員に割増賃金を支払う義務があるのか?
| Q 割増賃金の支払いに関しておたずねします。先日、当社の従業員が年俸制であっても時間外労働や休日労働などの割増賃金の支払いは必要なのではないかといってきました。当社としては、割増賃金分も含めて年俸を決定しているため、割増賃金の支払いは必要ないと考えているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。
|
| A 労働基準法第37条では、使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければならないとされています。そのため、年俸制の労働者であっても、時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
しかしながら、割増賃金相当分を含めて年俸額を決定することができないわけではありません。このことについて行政解釈では、「一般的には、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれている事が労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区分することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解かされる」とされています(平12・3・8基収第78号) つまり、就業規則や労働契約書等で、年俸額に割増賃金相当分が含まれていることが明確に規定されていれば、割増賃金相当分も年俸額に含まれているとみることができるわけです。 例えば、ある月に時間外労働を40時間した場合、その月の割増賃金相当分が30時間分(年間360時間)となっている場合には、年間で見て時間外労働が360時間以内であっても、その月については、別途10時間分の割増賃金の支払いが必要になります。 ご質問では、割増賃金分も含めて年俸を決定していると主張していますが、年俸のうち、割増賃金分が明確になっていない場合には、その根拠がないわけですから、時間外労働などの割増賃金は、年俸とは別に支払わなければなりません。 行政解釈でも、「年俸に割増賃金を含むとしていても、割増賃金相当額がどれほどになるのかが不明であるような場合及び労使双方の認識が一致しているとは言い難い場合については、労働基準法第37条違反として取り扱うこととする」とされています。 |
会社で二割負担した際の休業補償給付は
| Q 休業補償給付の事で伺います。先般、当社従業員が鉄材運搬中事故で左足を骨折し、全治一カ月の重傷を負いました。業務上の負傷として労災保険から平均賃金の八割相当額の休業補償がなされると思われますが、当社ではこの八割に二割分を上積みして十割の賃金保障をしようと考えています。しかし、健康保険の傷病手当金は会社が何割かの賃金を支払うとその分だけ減額されるころになっていますが、労働保険の場合はどうなっているのでしょうか。
その点を詳しく教えてください。 |
| A 六割未満の賃金支給なら休業補償は全額給付
労災保険法第十四条では、休業補償給付について、「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のためにろうどうすることができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする」としています。さらに、休業に対してはこの休業補償給付に加えて、労働福祉事業の一環として、休業特別支給金が給付基礎日額の百分の二十の額をもって支給されます(労災保険特別支給金支給規則) ところで、ご質問は貴社が休業補償給付に賃金を上積み支給する場合、労災保険の給付が健康保険と同様に制約されるかということのようです。労働基準法第七六条では労働が不能な場合に平均賃金の六割以上の賃金を支払った場合には使用者は休業補償を行わなくてもよいとしています。労災保険法の考え方もこれと同じで、会社が平均賃金の六割以上の賃金を支払えば、その日は「休業する日」とはみなされず、労災保険の休業補償給付は支給されません。逆に六割に満たない額の賃金を支給した場合は、労災保険法から休業補償給付が全額支給されるわけです。 ですから、会社が平均賃金の六割未満の額の賃金を支払ったとしても、労災保険からの支給が制限されるころはありません。極端は話ですが、会社が五割九分の賃金を支払っている場合は、労災保険からの休業特別支給金を含めて合計平均賃金の一三割九分の金額が被災者の手に入ることになるわけです。しかし、各企業での取り扱いを見ますと、ご質問の場合のように休業特別給付金を見込んで二割支給し、合計十割の賃金補償にするという規定が多いようです。 ご質問では、健康保険の傷病手当金のことを引き合いに出されていますが、傷病手当金については、「傷病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受け入れることができる者に対しては、これを受けることが出来る期間は、傷病手当金又は、出産手当金を支給しない。ただしその受け取ることができる報酬の額が、傷病手当金又は、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する」(健康保険法第一〇八条)と規定しています。すなわち、傷病手当金は会社から六割未満の賃金支給があれば、その分だけ減額されて支給されるわけです。この点、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の支給の仕方は異なっていますので、取り扱い上留意することが必要です。 |
通院費は支給されるか
| Q
通院費は支給されるか。
|
| A
労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に通院要した費用の実費相当額が支給されます。
1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
3 同一市町村及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
|
会社が休みの日でも休業補償をもらえるのか。
| Q
会社が休みの日でも休業補償をもらえるか。 |
| A
①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、 ②労働することができないため、 ③賃金をうけていない、 という要件を満たしていれば、会社し所定休日分も支給されます。 |
休憩時間中の災害は労災保険が適用されるか?
| Q 昼休み中に食事のため会社の外に出てケガをした。労災保険が適用されるか。 |
| A 休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が自由に利用することが許されており、その間の個々の行為自体は労働者の私的行為といえます。したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設(又はその管理)の状況(欠陥等)に起因することが証明されない限り、一般には業務起因性は認められませんので労災保険給付は受けられません。 |