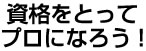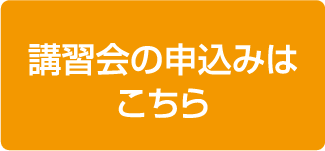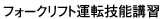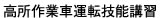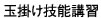自由研削といし特別教育 講習会申込予約フォームはこちらから
自由研削といしの取り換え、または取り換え時の試運転の業務に関する特別教育の開催のご案内
従業員を、標記業務に就業させる事業者は、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条1号により特別教育を行わなければなりません。
このたび、当協会では事業者に代わり、標記教育のうち「学科教育」及び「実技教育」を下記により実施いたしますので貴事業場の該当者を受講させていただきますようご案内いたします。
■講習内容
| 時刻 |
科目 |
| 9:00~11:00 |
自由研削用研削盤・といしの取り付け具等に関する知識 |
| 11:00~12:00 |
自由研削用といしの取り付け試運転の方法に関する知識 |
| 12:00~13:00 |
昼食休憩 |
| 13:00~14:00 |
関係法令 |
| 14:00~16:00 |
実技 |
| 16:00~16:10 |
終了チェックテストと解説 |
■講習日数 1日
■講習料金 会員(受講料8,000円・テキスト1,050円)非会員(受講料10,000円・テキスト1,050円)
■講習会場 講習月日により場所は異なります。日程表にて確認をお願いします。
■対象機器 動力により回転する研削といしを用いて、金属その他の加工物を研削又は切断する機械のうち加工物を手で送るか又は研削盤を手で持って加工する機械。
■次回日程 2月18日(火)