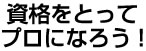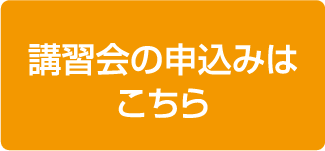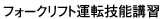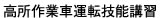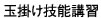| Q 仕事中にけがをしたが健康保険証を使って受診してしまった。 |
| A 健康保険から給付された額(7割)を健康保険に返還し、窓口負担分(3割)と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求(様式第7号)することになります。請求書に領収書・領収済証(10割分)を添付してください。 |
admin のすべての投稿
子育て支援について
| 西宮労働基準監督署
第一方面主任監督官 増田 |
| 最近のニュースで、俳優の東山紀之さんと女優の木村佳乃さんに女の子が生まれたというのがありました。記者会見で東山さんが、おむつ替えを手伝い、育児は共同作業だと「イクメン」宣言をしたのが印象的でした。
「イクメン」という言葉も普通に使われるようになってきていると感じました。 私事ですが、我が家にも3人の子供がおります。私は、結婚して子供が生まれるまではほとんど家事はしていませんでした。しかし、子供ができてからは、共働きであったことで、関わらざるを得なくなりました。 保育所のお迎えは、13年間続けましたし、家事・育児も徐々にやるようになりました。その中で、しんどいこともありましたし、子供が熱を出してどちらが休むかでけんかしたこともありました。 家事が上手になったとは言えませんが、育児は最初と比べると少しは楽しめるようになったと思います。 育児休業制度ができてから既に20年が経ち、少しづつ制度の改善が図られ、今は子供の看護休暇制度もできました。しかし、昨年の出生動向基本調査によると、夫婦の理想の子供の数は、2.42人ですが、予定子供数は2.07人となっています。予定が理想を下回る理由は、経済的理由が60%、ついで、年令上の問題が35%となっています。また、産前産後休暇や育児休業を取得する率は増加傾向にあります。 少子化対策が言われてから久しくなりますが、なかなか抜本的な改善には至ってないのが現状です。歯止めをかけるには、子育て世代への経済的な援助と休暇制度や保育所の増設などの制度の改善が活用できる環境整備と社会全体で子育てを支援をしていく意識を高める必要があると思います。 私は今、学童保育所の充実のために微力ですがお手伝いをしています。学童保育所は共働きや単身家庭の子供たちが小学校の放課後を過ごす生活の場として大切な役割がありますが、保育所の卒所児の6割弱しか新1年制が学童保育所に入っておらず、、「小1の壁」があると言われています。もっと、学童保育所を質・量ともに充実する必要があります。 今後、さらに国、自治体、企業、地域が協力し、若い人たちが子育てしやすい社会にしていければいいと思います。 |
運行管理者(貨物)受験準備講習
運行管理者(貨物)受験準備講習のご案内
平成24年3月4日及び8月26日実施予定の運行管理者試験合格のための受験準備のための講座です。
受験される方が効率よく実力を養成できるよう研修いたします。該当者は是非ご受講ください。
※なお3月の試験で不合格者及び8月の試験受験予定者は今回は有料ですが、7月に実施予定の同講習は無料で受講することができます。
1 日時
平成24年2月25日(土)9:30~16:30
2 会場
西宮勤労会館4階第8会議室
3 内容
・貨物自動車運送事業法 ・道路貨物者両方
・道路交通法 ・労働基準法 ・実務上の知識
4 講師
中野 真弓 氏 (社会保険労務士)
5 受講料
10,000円(テキスト代込)
7 申込締切日
2月20日
8 受講料
10,000円 (テキスト代・消費税込)
西宮労働安全衛生大会・新年祈願祭・兵庫第3回特配休暇セミナー
標記の件下記により開催いたします。多数ご参加いただきますようご案内いたします。
1 日時 平成24 年1月16 日(月)13:30~17:00
2 会場 西宮神社会館(西宮市社家町1-17)0798-23-3311
3 内容 ①兵庫第3回特配休暇セミナー(㈳兵庫労働基準連合会主催)
13:45~14:45
「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度について」
社会保険労務士 茶園幸子
②講演
14:45~15:15
「労働災害の防止について」
西宮労働基準監督署担当官
③特別講演
15:15~16:30
「祈りは谺 君は親指のような人間になれ」
天台宗繖山安楽寺住職 普照房慈弘
④安全衛生祈願(西宮神社)
16:40~17:10
⑤新春意見交換会
17:15~19:00
4参加費 無料(意見交換会参加者は5,000円)
5 定員 300名
6 申込先 西宮労働基準協会
〒662-0911 西宮市池田町4-28森川ビル2階
TEL:0798-33-4939 FAX:0798-33-2298
7 申込方法 (どなたでも参加できます)
FAXにて会社名・電話番号・FAX番号・担当者名・参加者名をご記入の上お申し込みください。
FAX番号 0798-33-2298
リスクアセスメント研修会
近年の労働災害発生状況をみると長期的には減少してきていますが、今なお多数の方が被災し、その減少には鈍化の傾向がみられます。
また、生産工程の多様化が進む中、新たな機械設備・化学物質の導入などにより、労働災害の発生もお複雑化しています。
この現状から、平成18年4月労働安全衛生法が改正され、事業者は危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが努力義務として規定されました。(第28条2)
つきましては、下記の要領でリスクアセスメント研修を開催いたしますので、 多数受講されその管理方法を高めていただくようご案内いたします。
講師には、中央労働災害防止協会、大阪安全衛生教育センター非常勤講師の去来川 敬治氏をお迎えいたします。
1 日時 平成26年2月21 日(金)9:30~17:00
2 会場 西宮勤労会館4階第8会議室
3 受講料 会員10,000円 非会員12,000円 (テキスト代・消費税込)
4 定員 50名
5 カリキュラム
| 時間割 | 科目・内容 |
| 9:30~9:40 | 受付 開講挨拶 |
| 9:40~10:40 | 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)について |
| 10:40~10:50 | 休憩 |
| 10:50~11:50 | リスクアセスメントの目的と意義 |
| 11:50~12:40 | 昼休憩 |
| 12:40~14:40 | リスクアセスメントの進め方 |
| 14:40~14:50 | 休憩 |
| 14:50~16:50 | リスクアセスメントの演習、まとめ |
| 16:50~17:00 | 修了証交付 |
6 申込先 西宮労働基準協会
〒662-0911 西宮市池田町4-28森川ビル2階
TEL:0798-33-4939 FAX:0798-33-2298
7 申込方法
FAXにて会社名・電話番号・FAX番号・担当者名・受講者・生年月日・本籍・住所をご記入の上お申し込みください。
丸のこ等取り扱い作業従事者教育
丸のこ等は建設現場のみならず製造業の現場でも広く使用されている便利な機械です。しかし反面丸のこ等の作業において多数の労働災害が発生し、死亡 災害に至るものも毎年発生している現状にあります。このことから「携帯用丸のこを使用する作業に従事する者に対する安全衛生教育の徹底についてが通達され、携帯用丸のこを使用する労働者には特別教育に準じた教育を実施することが求められております。当社は下記により当教育を実施いたします。該当者はご受講いただきまるようご案内いたします。
■講習料金 受講料
5,000円(税込)テキスト代1,000円(税込)
■講習会場 西宮市立勤労会館4階第8会議室
■内容 携帯用丸のこ盤に関する知識・作業に関する知識(2h)
安全な作業方法に関する知識・点検及び設備に関する知識(1h)
関係法令(0.5h)
実技(0.5h)
■定員 40名(先着順・定員になり次第締め切ります)
■次回開催は平成23年11月22日(火)
清掃作業中自動車に轢かれ死亡
| 業種:清掃業
被害:死亡1名 |
| 災害発生状況
当時の天候は、小雨であり、薄暗い状況であった。被災者は、駐車場入り口を横断する側溝のグレーチング(格子状蓋)を取り外し、しゃがみこむ姿勢で側溝右側付近の内部の清掃を行っていた。 この時、当該駐車場に入るため、駐車場に向かって右方向から普通自動車(加害車両)が右折して来たため、同自動車に轢かれ死亡したもの。 発生場所の状況 発生場所は駐車場入り口で、センターライン無しの6m道路からT字状に入り口がある。入口から向かって左側が車両の駐車スペースで右側は駐車操作等のための道路である。駐車場周囲と道路は縁石があり、これに沿って、高さ約75cmの生垣が植栽されている。 災害発生原因 被災者の位置・姿勢は、加害車両位置の運転者からは、生垣と車両のピラーによる死角に入り、被災者はほとんど視認出来ない。また、被災者からも走行してきた車両は視認出来ず、双方が視界に入っていた。発生時の車両の走行速度は時速5km程度で、駐車操作を容易にするため道路の比較的右側を走行し、右側の生垣に沿うように駐車場へ向け右折したため、運転者からの死角はさらに広がった。 再発防止対策 1 車両が行った右折動作は、いわゆる「右折の早回り」であり死角が増え、事故の原因となる。本来右折動作は交差部中央付近まで十分に直進し、進行方向の状況を確認した後に右折動作を開始することが基本である。今回も本来の車両位置であれば作業を行っている被災者を視認出来た可能性が高い。 2 時速5kmは徐行と考えられ、その停止距離は約1.24m程度であり、駐車場通路の全幅を視認してから右折すれば、被災者と接触する前、または接触したとしても最悪の事態は避け得た可能性が高い。 3 作業中は通行を遮断し、警備員等を配置することが最も望ましい措置である。 4 作業予定箇所・日時の周知を徹底する、作業箇所付近に作業中である旨の表示を行い、注意喚起する必要があると考えられる。 |
日射病と診断されたが労災として認められるか?
| Q 真夏の炎天下の中、土木作業に従事していたところ、身体の異常を感じそのまま作業を続けていると、しばらくすると倒れてしまいました。医師から「日射病」と診断されましたが労災として認められるでしょうか。 |
| A 職業性疾病の場合、負傷とは異なり、その業務起因性を判断することが容易ではありません。しかしながら、職業性疾病の中には業務との因果関係が一般的に認められるにいたっているものもあるため、労働基準法第75条第2項で、これらの疾病を具体的に厚生労働省令で定めることとされ、労働基準法施行規則第35条別表1の2において、第1号から第7号まで類型的に業務上疾病の範囲が定められています。この規定は、人の健康を害することの医学的知見から得られている有害因子とその有害因子によって引き起こされることが明らかとなっている疾病を網羅しているもので、この規定に該当することについての一定の要件を満たしておれば、それが他の原因で生じたおのであること等の積極的な立証がなされない限り法令上業務上疾病とみなされます。また別表には、その他将来的に疾病を追加する必要のあることを考慮して第8号に「厚生労働大臣の指定する疾病」、第9号に「その他業務に起因することの明らかな疾病」を設けて、個々の事例に則して業務起因性があると認められた疾病を補償の対象と得る途をも残す方法をとっています。今回の「日射病」につきましては、この別表第2号8に定められている「暑熱な場所における業務による熱中症」に該当するか否か検討されることになります。まず暑熱な場所についてですが、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所で、例えば夏季の屋外労働、炉前作業に係る業務等があります。
次に熱中症ですが、前駆症状として、頭痛、めまい、耳鳴り、疲労、欠伸、朦朧感などがあり、発汗は停止し、著しい体温上昇とともに突然意識障害をきたすもので、「日射病」・「熱射病」も含まれます。ただ、頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害もあり、「日射病」であったか否かについては、確認する必要があります。また、この熱中症の罹患には、体質、身体条件等も影響し、特に不眠、疲労、脚気、発汗の特に少ない体質等の者はなりやすいと言われており、夏季においては高温多湿となるたま、一般労働者においても罹患する可能性があります。ので、今回、炎天下での作業時に発症したとのことですが、当日の作業環境、労働時間、作業内容、被服の状況、その他作業場の温湿度等から暑熱な場所での作業であり、身体の状況から他の原因により発症したものではなく、日射病の確かな医学的診断があれば労災として認められるでしょうが、最寄りの監督署へ相談されることをお勧めします。
|
会社都合で1日の所定労働時間の一部を休業させた場合の休業手当の計算方法
| Q 労基法には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中労働者に平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならない。」旨規定がありますが、この「休業期間」は、時間単位でみるのか、1日単位でみるのか、すなわち会社都合で所定労働時間の一部を休業させた場合、実際に働いた時間分の賃金の他に、休業時間部分に対して、時間単位で休業手当を支払わなければならないのか、あるいは、その一部休業した日全体について、平均賃金の百分の六十の休業手当を支払えばよいのでしょうか? |
| A 労働基準法第26条では、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。ご質問の件については、「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の百分の六十に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。」(昭和27年8月7日基収第345号)との通達により行政解釈が示されており、後者の立場をとっています。この行政解釈を反対の言い方をすれば、「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の百分の六十に相当する金額以上の場合には、この賃金以外に別途休業手当を支払わなくてもよい。」ということになります。
「1日のうち一部での休業させておきながら、休業手当を支払わなくてもよいというのは不合理ではないか」との考え方もあると思いますが、そもそも、休業手当は労働者の最低生活を保護するために設けられたものであり、そのために平均賃金の百分の六十を最低基準として労働者に保障しているものなので、この基準を超える部分の支払いについては、民法の考え方に基づいて労使間で取り決めていただくこととなります。
|
「9.11」
| 株式会社 永瀬 代表取締役専務
永瀬 隆一 |
| 2001年9月11日、某日経会社のニューヨーク支店に勤めていた私は朝一番の配送の為、アメリカ人パートナーが運転するトラックの助手席に座りターンバイクを北上していたところ、ふいにラジオから聞こえてきたニュースに耳を疑った。マンハッタン市内で飛行機事故発生、世界貿易センタービルにジャンボ機が突入、炎上。続報を待つうちに2件目の配送に向かう。リバーロードを南下する私達は衝撃的な光景に息を飲む。ハドソン川を隔てて1キロ先に見えるツインタワーから灰色の煙が立ち昇り、近辺のビル群も煙に覆われていた。川沿いにトラックを停めた私達は呆然と眺めていたが、気がつけば私の目からは涙が溢れていた。事態は詳しく理解していないが、あの煙の中では何百何千の尊い命が奪われていることは想像できたからである。15年前に芦屋で体験した阪神大震災の時の情景が再現され、圧倒的な力の前では何も出来ない絶望的な涙であった。その後、飛行機事故が報復の為のテロ行為だと判明し、震災の時とは全く違うことを思い知らされる。テロ当日の午後からマンハッタンは厳重な警戒態勢が布かれ進入経路には全て検問所が置かれた。数日後私もライフル銃を持った兵士に身元を調査されてマンハッタンに入った。テロにより命を落とした日本人駐在員の遺族の帰国準備を手配するためである。56丁目に面した高級アパートにはガックリと方を落とした未亡人と無邪気にはしゃいでいる幼い子供がいた。おそらく子供は父親を亡くしたことを理解していないのだろう。純粋に輝くその瞳が心に痛かった。その時、私はこう思った。この子が成長して全てを理解した時、父の死を受け入れることが出来るだろうか?人種や国籍を問わず人を信頼することが出来るだろうか?
いずれも数千人の命を失った痛ましい事件であったが、地震は天災であった。人の力ではどうしようもなく、それが理解できるからこそ阪神間の人々は必死で前向きに復興に尽力することが出来たのだと思う。しかしながら9年前のテロは明らかに人が意図的に起こした戦争である。戦争を体験することが少ない世代に生まれながら、不幸にも他国の戦争の犠牲になってしまった人々の気持ちを考えるとやり場のない怒りが込み上げてくる。 偶然にも2つの大きな事故に遭遇したが、今でも9月になるとニューヨークのことをよく思い出す。あのときの子供の目は今も光輝いているだろうか、と。 |